第16回 全国に先駆けて労働者協同組合の設立を支援した自治体の取組み(京都府京丹後市)
(2024年12月掲載)
京丹後市では、2023年12月に全国で初めて公務員が発起人となった労働者協同組合TANGO CREW'Sが誕生しました。その背景には、地域課題解決の手段として全国に先駆けて労働者協同組合の周知や設立支援に取り組んだ京丹後市の施策があります。
今回はこの取り組みの立役者であり京丹後市市長公室地域コミュニティ推進課の職員として労働者協同組合立上げを支援しているHさんと、京丹後市ふるさと創生職員※1でもあり、労働者協同組合TANGO CREW'Sを立ち上げた代表理事のMさんにお話を伺いました。

京丹後市の多様化する課題〜稼ぐことで持続可能な地域をつくる〜

京丹後市は2004年に6つの町が合併して誕生しました。京都府の最北端・丹後半島に位置し、東西約35km、南北約30kmの広がりを持っています。
2015年には5万人を超えていた人口が、2045年には3万2千人へと減少し、概ね 2人に1人が65歳以上になると予想されています。2006年には12箇所だった限界集落も、2021年には38箇所に増え、10年間で約3倍に増加しました。
一方、人口減少の影響で、環境整備や防災活動、高齢者の見守り、お祭りや子ども会の運営など、これまでは自治会が主体となり行ってきた地域活動の継続が課題になっています。また、旧町ごとや、その中でも市街地と農村部など、地域ごとに自治の成り立ちや課題も様々です。
加えて、民間企業の撤退により買い物や移動など高齢者の生活支援が課題となる他、世帯構成の変化により空き家も増加するなど、地域課題が多様化しています。
このような地域課題の深刻化を見据え、同市では2021年度に地域コミュニティ推進課を設置。若者や女性など多様な人材が活躍し、主体的に地域振興や課題解決に取り組む地域を目指して、「新たな地域コミュニティ推進事業」をはじめました。
この事業は、旧校区や旧村など複数の自治区にまたがる広域な範囲で新たな地域コミュニティをつくり、地域が主体的に行う課題解決や取り組みを支援するものです。2021年度には6つだったモデル地域は2023年度には20を超え、若者や女性、そして地域外の協力者など多様な人たちが関わることで活動が多様になりコミュニティが活性化しています。
しかし、その多くはボランティアベースであり、自治体の補助金によって運営されていることから、持続性が課題となっています。そこで同市では地域の稼ぐ力の強化として、地域課題の解決や地域づくりを仕事にするため、労働者協同組合に注目しました。

「地域コミュニティ推進課が設置され、地域の力で地域課題を解決していく方法を模索していた頃、ちょうど同じタイミングで労働者協同組合が制度化されました。この制度なら、私たちが目指す稼ぐ地域を実現する上で有効なのではないかと考え、全国に先駆けて予算化し制度の周知や設立支援を始めました」と同市職員のHさんは当時を振り返ります。
さらに、「市民活動の多くはメンバー同士がフラットな関係性の中で活動しているため、株式会社やNPO法人などの法人格へのステップアップは、メンバー間に上下関係が生まれてしまうかもしれず、二の足を踏んでいる団体もありました。労働者協同組合は、すべての組合員が出資し経営にも関わるため、団体メンバーがフラットな関係性のまま法人にできる点もメリットだと考えています」とHさんはいいます。実際、同市が開催した労働者協同組合設立支援の施策は、地域住民から注目を集めました。
延べ200人の京丹後市民が参加した「まちづくり研修会」

地域団体を対象とした労働者協同組合設立に関する相談会には、農地保全、海岸美化、加工品、障がい者支援等延べ12団体が参加しました。
市職員を対象とした説明会には7部署23課39人が参加したほか、地域おこし協力隊やふるさと創生職員を対象とした説明会も実施し制度を紹介しました。市民を対象にした「まちづくり研修会」には延べ200人が参加し、高い関心が寄せられました。
「参加者からは『労働者協同組合は新しい制度なので可能性を感じる』との声もあり、『まちづくりを仕事にする』というキーワードが響いたようです。特に忙しい世代の若い人たちにとっては、まちづくりに取り組みたいと思ってもビジネスとしてやっていく糸口がなければ継続は困難です。『この制度をうまく活用できれば、自身の仕事に加えて、副業として自分の住むまちが抱える課題解決や、自分が本当にやりたいことを実現することができるかもしれない』という参加者からの感想もあり、この制度の可能性を感じました」とHさんは語ります。
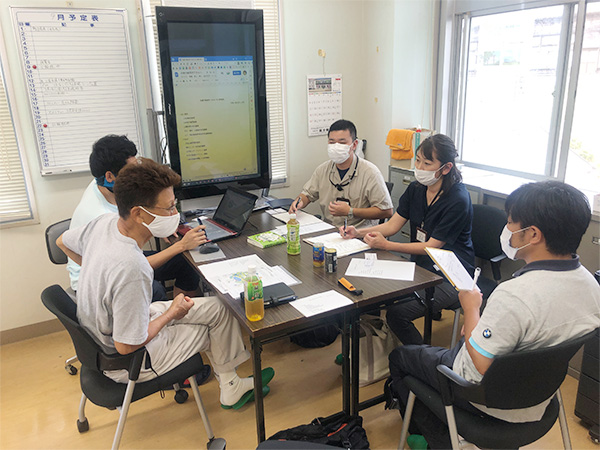
他にも同市では、労働者協同組合の理念に関する理解や定款・事業計画の作成について知見を有するコーディネーターを配置し体制を整えています。また、農産物の加工品をつくっている加工所や自治会など、労働者協同組合の設立に関心のある団体へコーディネーターが入り伴走支援を行っています。2023年度には3団体の支援を行いました。
そのうちの1つが、昨年12月に設立された、京都府初であり、公務員が発起人となった全国初の労働者協同者組合TANGO CREW‘Sです。
公務員が副業として設立した労働者協同組合TANGO CREW'S
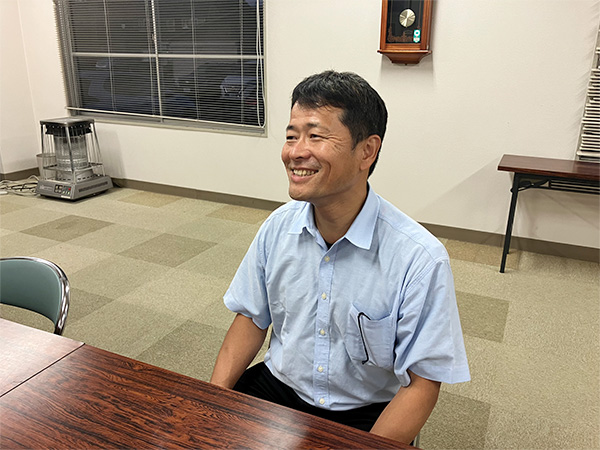
TANGO CREW'Sを設立した中心メンバーは京丹後市でふるさと創生職員として働いていた人たちで、2年半前に移住したMさんもその一人でした。
ふるさと創生職員は、副業ができるとはいえ身分上では公務員。職種に制限があり、地域おこし協力隊と比べても圧倒的に自由度が低く、任期を終えた後に定住するための仕事が見つからない可能性があるといった課題もありました。
もともと京丹後市には移住する気持ちで来ていたため、いずれは個人事業主になること、あるいは法人を設立しようと考えていたMさん。他のふるさと創生職員と地域課題解決を事業として行うため、様々な法人格を検討していましたが、その中で労働者協同組合を選んだのには理由がありました。
それは、メンバーである職員たちの実現したいことや得意分野が異なっており、地域にたくさんある課題の解決を具体的なひとつの事業にまとめることが難しかったためです。加えて、労働者協同組合にすれば同市が設立などを支援してくれるだけでなく、「もし問題があれば組織を変更すればいい」と市のセミナーで得た知識から背中を押されたといいます。
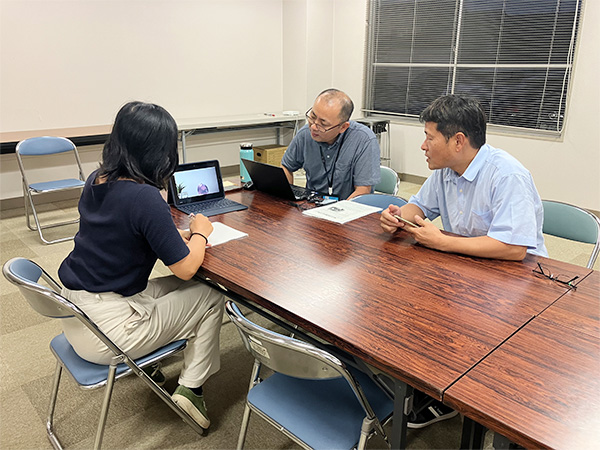
TANGO CREW'Sでは協同労働のコンセプトのもと、月に1度集まり進捗会議を行い、皆が納得したうえで事業を進めることを大切にしています。
また、8人から成るメンバーの強みに合わせた内容を部門化してプロジェクトリーダーをおき、事業を完結するやり方をとっています。担当制にすると専門性があがり仕事の進みが早くなります。事業化するためにスピードを重視しているため、この方法をとっていますが、担当制により生じる「フォローしあえない」というデメリットは、進捗会議の場で解消しています。

「公務員として働く中で地域の様々な課題に直面しますが、公務員の立場では特定の地域や相手を支援することは難しい一面もあります。しかし、労働者協同組合の形であれば制約がなくなり比較的自由に動けます。現在はTANGO CREW’Sとしての取り組みの半分は非営利のボランティアとして行っていますが、地域の方々が喜んでくれるので、“やりがい”につながっています。自分たちでまちをつくっていかないといけないと感じているので、将来的には空き家・空き店舗活用、商店街や道の駅などをハブとした地域活性化、都心への特産物販売などにも取り組みたいと思っています。いずれは、高齢者の見守りや移動支援など行政と連携できるような道が見つかれば」とMさんは今後展開していきたいアイデアを語ってくれました。
京丹後市、今後の展望と課題

同市では、高齢化する住民への買い物や移動支援のため、国が推進する日本版ライドシェア「自家用車活用事業※2」に取り組もうと、自ら旗を振ってドライバーの募集をしています。
近年、スーパーの撤退や公共交通機関の廃止により、住民の生活に支障が出てきている地域もあります。一方で、戸数の少ない地域への物流も民間企業では採算が取れなくなっているのも現状です。
「例えば市民の交通手段を解決することが、高齢者の見守りや通院のサポートにも同時につながるような、複数の地域課題を解決できる労働者協同組合があると、行政としても協働できるとかもしれないと考えています」とHさん。
同市では、今年も周知のために「地域しごとづくり協同労働セミナー~『協同労働」で稼ぐとは?~」を開催しますが、既に労働者協同組合の設立に興味を持っているグループもあります。自ら仕事をつくり地域課題を解決していけるような地域を目指して、今後も労働者協同組合設立の伴走支援を続けていきます。
※1「京丹後市ふるさと創生職員」とは
3年間の任期付短時間勤務職員。市外からの移住者を対象に副業が可能な地方公務員として公募を行うもので、多様な人材の活躍、新しい働き方の可能性を拡げ、任期終了後の定住を推進するもの。
※2「日本版ライドシェア『自家用車活用事業』」とは
タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して有償で運送サービスを提供するものであり、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」とする取扱いで本年4月1日より実施。
