第12回 顔の見える関係性をつくり、暮らしやすい地域を目指す
労働者協同組合(板橋区)
(2024年9月掲載)

板橋区で介護保険事業のリハビリデイサービスを運営しているエイトバードカンパニー労働者協同組合を紹介します。地域の人々を巻き込みながら運営することで顔見知りを増やし、どんな人でも暮らしやすい地域づくりを目指しています。将来的には地域の子どもの居場所づくりや、ヤングケアラー支援等の社会事業の展開も視野に入れているとのこと。団体設立のきっかけやこれからの展望について、代表のMさんにお話を伺いました。
立上げの背景〜地域の困りごとを解決〜
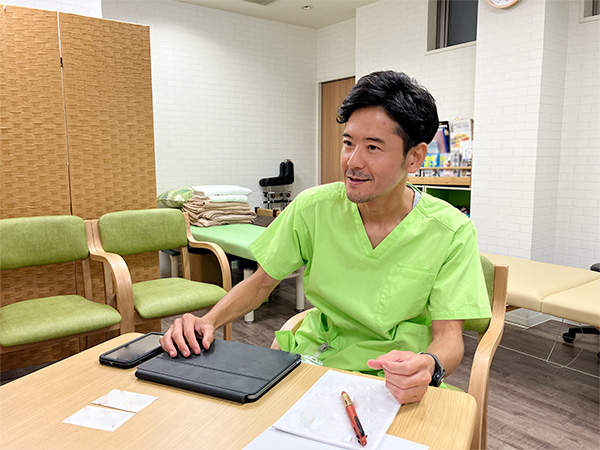
この法人の立上げのきっかけに「施設や病院といった場所ではなく、住みなれた地域で暮らすのが理想」という思いがあったと、Mさんは語ります。大学で地域福祉を専攻していたMさん。卒業後には、障がいを持つ子どもの親御さんたちが、障がいがあっても地域で暮らせるように立ち上げたNPO法人で働き始めます。地域での困りごとを地域の人々を巻き込みながら解決していく事業に関わる中で、法人の立ち上げに関心を持つようになりました。
その後、急性期・回復期の患者のリハビリを行う病院で働く中で、多くの患者さんが退院後に困りごとを抱えながら生活していることを知りました。例えば、別の地域から引っ越してきたため周りに知り合いが居らず、行政手続きが分からなくても誰にも助けを求められないケース等、多くの困りごとを目にしてきたそうです。
このような経験から、「地域の中で顔見知りになって助け合える社会を作れたら、色々な課題が解決していくのかもしれない」と思い、Mさん自ら法人を立上げようと考えました。
事業としてデイサービスを選択〜資格や経験を活かした事業展開〜

Mさんと一緒に法人を立上げた組合員の1人であり、元々は病院で理学療法士として働いていたTさん。ライフ・ワーク・バランスが崩れがちだった働き方に悩んでいた時期にMさんから声をかけられました。Tさんは「全員が出資者で労働者」という仕組みに賛同し、一緒に労働者協同組合の立上げを行いました。ただ、最初から事業としてデイサービスを行うと決めていたわけではありませんでした。地域で顔の見える関係性をつくるような社会貢献事業を行うためには法人を維持する収益が必要です。
そこで、Mさん自身の社会福祉士・作業療法士の資格やリハビリ専門職としての経験、Tさんの理学療法士としての経験から、根幹の収益事業としてデイサービスを選択しました。
Tさんは前職の働き方を振り返りながら「ここでは自主的に休暇を取ることができるなど、メンバーそれぞれが働きやすい。経営者としてしっかり利益を上げて仕事をするという意識や、働き方についても考えられるところに惹かれた」と話します。
労働者協同組合を選択した理由〜経営者と労働者と出資者が三位一体の運営〜

Mさんは、かつて病院に勤務していた時、経営者と労働者の間には大きな意識の違いがあることに気づきました。経営者側は運営資金に対してシビアな考えを持っているのに対し、現場の労働者は運営資金面にまで意識が及ばず、認識のずれが生じるのです。経営者である雇用者と労働者である被雇用者間の目標や利益が一致せず、乖離が生まれてしまうことをプリンシパル・エージェント問題といいます。この問題はどの法人格でも身近な課題だといわれています。Mさんは、双方の意識が乖離し、組織全体が上手くいっていない状態を目の当たりにしてきたからこそ、経営者と労働者と出資者が三位一体になっている労働者協同組合ならば、その問題を解決できるのではないかと考えました。
労働者協同組合は全員が出資することで、皆が経営者で労働者であるという点から、運営資金について当事者意識を持ちやすいといわれています。組合員のTさんも「自分が提供するサービスの質が良ければ利用者の満足度が高く、利用者数が増えると給与にも反映される。自分の働き方そのものが経営に直結する」と言います。Tさんは収益を上げるためにサービスの向上はもちろん、備品など細かいものについても意識するようになりました。

他にも組合員同士で収益を上げるために、既存の利用者が利用回数を増やしてくれるように、質が高く利用しやすいサービスのあり方について考えました。例えば、以前ケアマネージャーとして働いていた組合員からは、事業者に空き状況をFAXするアイディアの提案があり、利用率の改善もありました。このように、メンバー全員で経営について考えることができるのは、労働者協同組合の強みだとMさんとTさんは口を揃えて言います。
これからの展望〜暮らしやすい地域づくりの実現に向けて〜

「助け合いが出来て暮らしやすい地域づくり」の実現へ向けて、先日、『いたばし認知笑(にんちしょう)カルタ大会』の開催を企画したところ、障がいの有無に関わらず、デイサービスの利用者のほか、地域の子どもたちや近隣住民が参加しました。大会ではデイサービスの利用者がカルタの札を読み、子どもたちが札をとる流れで行います。この背景には、「子どもたちが認知症について理解することで、地域で認知症の症状で困っている人を見かけたら声をかけてほしい」というMさんの思いが込められています。その結果、カルタを通して楽しく交流する中で、地域の顔見知りの関係を築くことに成功したのです。
「病院で働く中で困りごとを抱えているヤングケアラーにもたくさん出会ってきました。将来的にはヤングケアラーの支援事業も行なっていきたいが、実績がないと自治体から事業委託を受けることが難しい。そのため、まずは子どもの学習支援や子ども食堂を行うことで実績をつくっていきたい。」と今後の展望について熱く語ってくれました。今後も、どんな人でも暮らしやすい地域をつくるために、地域の人々を巻き込みながら様々なイベントや事業を企画・運営していくとのことです。
